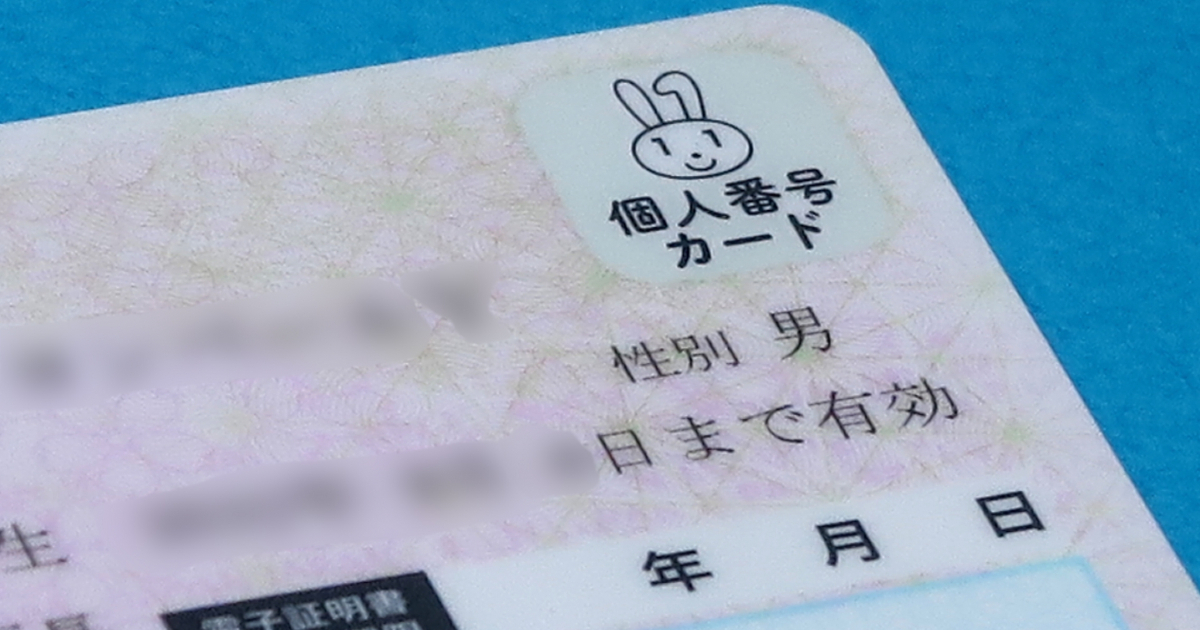「マイナンバーカードを落としてしまった…!」
そんなとき、胸がざわざわして落ち着かなくなるのは自然なことです。
急いで行動したい気持ちはわかりますが、間違った対応をすると、かえって時間や手間がかかってしまうこともあります。
この記事では、紛失が判明した直後にまず行うべき応急対応から、警察や役所での正式な手続きの流れ、さらに今後同じ失敗をしないための予防のコツまで、ひとつずつ丁寧に解説します。
専門用語や難しい制度も、初めての方でも安心して読めるよう、やさしい言葉で説明していますので、最後まで読めば「もしものときに何をすべきか」がしっかりイメージできるようになります。
マイナカード紛失が発覚したら最初にすべきこと

落ち着くことが第一歩
慌てると行動がちぐはぐになり、結果的に対応が遅れてしまうこともあります。
まずは深呼吸をして心を落ち着け、自分が今どこにいて、いつからカードが手元にないのかを静かに確認しましょう。
慌てたまま行動すると、確認漏れや重要な情報の見落としが起こりやすくなります。
特に外出先で紛失に気づいた場合は、その場で少し立ち止まり、バッグや財布の中、ポケット、最近使ったカバンや小物入れなどを丁寧にチェックしてください。
可能であれば周囲の人や同行者にも状況を説明し、一緒に探してもらうと見つかる可能性が高まります。
この最初の冷静な一歩が、その後の手続きをスムーズに進める大切な土台になります。
思い当たる場所をメモする
「最後にカードを使った場所」「行ったルート」「立ち寄ったお店」などを時系列でメモに残しましょう。
できれば、そのときの時間帯や一緒にいた人、利用した交通手段など、関連する細かい情報も書き出すとより役立ちます。
思い出して紙やスマホに記録する作業は、頭の中を整理する助けになり、忘れかけていた行動や場所が浮かび上がることもあります。
また、後から警察や役所に説明するときにも、具体的な記録があれば手続きがスムーズになります。
この段階でできる限り情報を残しておくことが、カード発見の可能性を高めるだけでなく、後の対応を楽にしてくれるのです。
不正利用の危険性を理解する
マイナンバーカードは身分証明や行政サービスの利用に使える、大切な個人情報のカギのような存在です。
紛失したまま長時間放置してしまうと、他人に拾われてなりすましに利用されたり、悪用されて公的な手続きや金融取引に使われてしまう可能性があります。
特に、オンラインでの本人確認や各種申請サービスに使えるため、被害が発生すると解決に多大な労力と時間がかかることもあります。
こうした被害は、カードの機能を早めに停止することで防げるケースが多いので、「見つかるかもしれないから…」と様子を見ず、速やかに停止や届出の対応を行うことが何より重要です。
マイナンバー悪用防止のための緊急停止方法

マイナンバー総合フリーダイヤルでの停止
専用窓口に電話をすることで、カードの電子証明書機能や公的個人認証などの利用を一時的に止めることができます。
これは、拾った人や第三者による不正利用を防ぐために非常に有効です。
・電話番号:0120-95-0178(24時間受付)
・ガイダンスに従い、紛失・盗難の停止を選択します。
案内の途中で本人確認のために氏名や生年月日、住所などを聞かれる場合があるので、あらかじめメモを用意しておくと安心です。
・深夜や早朝でも対応してくれるため、紛失に気づいたら時間帯を気にせずすぐに連絡しましょう。
電話がつながりにくい場合は、何度か時間をあけてかけ直すこともポイントです。
この連絡を済ませておくことで、その後の再発行や警察届出の際にも「すでに悪用を防ぐ処置を取った」という安心感につながります。
オンラインでの一時停止(マイナポータル)
パソコンやスマホからも停止手続きが可能です。
マイナポータルにアクセスし、画面の案内に沿って操作します。
操作方法は比較的シンプルですが、事前にログインに必要な情報(利用者証明用電子証明書やパスワードなど)を手元に用意しておくとスムーズです。
特にスマホの場合は、マイナポータルアプリをインストールしてから手続きを行うと便利です。
インターネット環境が安定している場所で行い、途中で接続が切れないよう注意しましょう。
また、オンライン停止は24時間対応しているため、夜間や休日でも手続きが可能です。
急ぎの場合や電話が混み合ってつながらないときには、この方法が大きな助けになります。
停止手続きが完了したかの確認
手続き後は、必ず「停止完了」の案内やメールが届いているかを確認しましょう。
メールが届かない場合や案内が表示されなかった場合は、手続きが正常に完了していない可能性があります。
その場合は、再度手続きを行うか、窓口やコールセンターに問い合わせて状況を確認しましょう。
あわせて、マイナポータル上でカードの利用状況を確認できる場合は、実際に停止状態になっているかをチェックすると安心です。
この確認を怠ると、停止できていないまま放置してしまう危険があるため、必ず最後まで確かめる習慣をつけてください。
警察への遺失届はなぜ必要?

受理番号が後の手続きに必須
再発行申請の際、多くの自治体で警察の受理番号が必要になります。
この受理番号は、正式に警察に紛失を届け出た証明となるもので、役所側も「確かに届出がされている」ことを確認するために使われます。
さらに、受理番号があると、後にカードが発見された場合や紛失に関連するトラブルが発生したときに、紛失時の記録を照合しやすくなります。
警察は遺失物としての届出を受けることで、拾得物が届けられた際に持ち主にスムーズに連絡できる仕組みを持っています。
そのため、受理番号を取得しておくことは、カードを早く取り戻す可能性を高めると同時に、手続き全般の安全性と信頼性を確保するうえで欠かせないステップです。
交番でも警察署でもOK
最寄りの交番や警察署に行き、事情を説明して遺失届を提出しましょう。
どちらでも手続きは可能ですが、警察署のほうが規模が大きく、担当部署が明確なため手続きがスムーズな場合もあります。
交番の場合はその場で事情を聞かれ、必要に応じて警察署に回されることもありますので、状況や時間に応じて行き先を選ぶと良いでしょう。
訪問の際は、身分証明書やメモした紛失日時・場所などを持参すると手続きがより早く進みます。
届出で聞かれる主な内容
・紛失日時
できるだけ正確な日時を伝えましょう。おおよその時間帯でも構いませんが、詳しいほど捜索や確認がしやすくなります。
・紛失場所
駅やバス、商業施設、路上など、心当たりのある場所を具体的に説明します。移動経路や寄り道した場所も伝えると役立ちます。
・カードの種類や特徴
マイナンバーカードであること、色や外観、ケースに入れていたかどうかなども補足します。
その他、裏面の記載内容やシールの有無など、思い出せる範囲で細かく説明することで、警察が見つけた際に本人確認がスムーズになります。
市区町村での再発行手続き

申請場所と担当窓口
お住まいの市区町村役所の窓口で手続きを行います。
多くの場合、市民課や戸籍住民課など、住民票や身分証明書関連の業務を扱う部署が担当です。
事前にホームページや電話で担当部署と受付時間を確認しておくと安心です。
混雑する時間帯を避けて行くことで待ち時間を短縮できることもあります。
必要に応じて整理券方式や予約制度を採用している自治体もあるので、あらかじめ調べてから向かうとスムーズです。
必要書類
・本人確認書類(運転免許証など)
顔写真付きの公的身分証が望ましいですが、持っていない場合は健康保険証や年金手帳など、複数の書類を組み合わせて提示することで代用できるケースもあります。
・警察の受理番号が分かる書類
遺失届を出した際にもらえる控えやメモなど、受理番号が明記されたものを用意します。
これがないと再発行手続きが進まない自治体もあるため、紛失しないよう注意が必要です。
・印鑑(必要な場合あり)
自治体によっては署名で代用できる場合もありますが、念のためシャチハタ以外の印鑑を持参すると安心です。
事前にホームページや電話で必要かどうかを確認しておくと無駄足になりません。
再発行にかかる費用と日数
・費用
おおむね800円程度が一般的ですが、自治体によっては若干の差があります。
手数料が免除になる条件(生活保護受給者など)を設けている場合もあるので、事前に確認するとよいでしょう。
・期間
約3〜4週間(自治体により異なる)。
繁忙期や申請件数の増加、書類の不備などがあると、1か月以上かかることもあります。
受け取りの際には本人確認書類が必要で、郵送ではなく窓口での受け取りが原則となるため、スケジュールにも余裕を持って申請することがおすすめです。
代理申請は可能?
代理人による申請も可能ですが、その際には委任状や追加書類が必要になる場合があります。
委任状には、申請者本人の署名や押印が求められることが多く、書式が自治体ごとに決まっている場合もあります。
また、代理人の本人確認書類や、申請者との関係性を証明する書類(家族であれば戸籍謄本など)が必要になるケースもあります。
さらに、代理申請を行えるのは配偶者や同居の家族など条件がある自治体もあるため、事前にホームページや電話で詳細を確認しておくと安心です。
再発行後の注意点

マイナンバー自体は変わらない
カードを再発行しても、マイナンバーは同じです。
つまり、番号そのものは一生変わらないため、万一カードが悪用されるリスクを考えた場合も、番号変更は基本的にできないという点を覚えておきましょう(やむを得ない場合を除く)。
このため、再発行後は引き続きカードや番号の管理に十分注意することが必要です。
また、再発行でカードの有効期限や電子証明書の期限がリセットされるわけではない場合もあるため、証明書の更新時期についても確認しておくと安心です。
公的機関や金融機関への届け出
マイナンバーカードを本人確認に利用している銀行口座やサービスがある場合、再発行後のカード情報を必ず更新しましょう。
たとえば、銀行口座の本人確認書類や証券口座、保険契約、年金関連のオンライン手続きなど、カード情報が登録されているサービスは意外と多いものです。
更新を怠ると、取引や手続きが一時的にできなくなったり、再度の本人確認が求められることがあります。
再発行後は、まず利用頻度の高い金融機関や公的サービスから順に、情報更新や再登録を行うと効率的です。
必要な場合は窓口で直接対応してもらえるほか、オンラインで手続きできるケースも多いので、事前に方法を確認しておくとスムーズです。
古いカードが見つかった場合
古いカードは使わず、必ず市区町村窓口に返却してください。
再発行後に古いカードを使用すると、機能が無効化されている場合でも誤解やトラブルの原因になることがあります。
また、古いカードには個人情報が含まれているため、適切に回収・廃棄してもらうことが重要です。
自治体窓口では、返却時に受領確認や廃棄手続きを行ってくれるので、紛失後に見つかった場合はできるだけ早めに持参しましょう。
マイナカードと運転免許証を一体化している場合の注意点と対処法

紛失時の影響
マイナンバーカードと運転免許証が一体化している場合、カードを紛失すると身分証明と運転免許証の両方を同時に失うことになります。
これは、単なる身分証の紛失だけでなく、自動車の運転資格そのものを証明できなくなるという重大な影響を伴います。
結果として、自動車の運転が一時的にできなくなったり、金融機関での口座開設や各種契約など、身分証が必要な手続きが滞る恐れがあります。
場合によっては、仕事や日常生活に大きな支障をきたすことも考えられます。
そのため、紛失に気づいたら直ちにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してカードの機能を停止すると同時に、警察への遺失届を速やかに行い、受理番号を取得しておくことが重要です。
再発行の手順
紛失時は、マイナンバーカードの再発行手続きと同時に運転免許証の再発行手続きも必要になります。
多くの場合、これらは別々の窓口で行う必要があるため、移動時間や待ち時間を含めると想定以上に時間と手間がかかります。
さらに、自治体窓口と運転免許センターの受付時間や休日が異なる場合もあるため、事前に営業日や受付時間をしっかり調べておくことが重要です。
必要書類としては、本人確認書類、写真、警察の受理番号に加え、場合によっては印鑑や申請書の事前記入が求められることもあります。
スムーズに手続きを進めるためには、可能であれば事前予約制度を利用し、スケジュールに十分な余裕を持って計画的に対応しましょう。
再発行後の再設定
新しいマイナンバーカード兼運転免許証を受け取ったら、以前に免許証情報を登録していたサービスや手続きを改めて再設定する必要があります。
例えば、レンタカー会員登録や保険契約、職場での身分証登録、カーシェアリングサービス、ジムや会員制施設での本人確認手続きなどが該当します。
これらの情報が更新されないままだと、サービスが一時的に利用できなかったり、契約更新ができないなどの不便が生じる可能性があります。
また、オンラインで免許証情報を入力している金融サービスやポイントプログラムなども対象になる場合があるため、リストアップして一つずつ確認しましょう。
再発行後は、なるべく早く確認・更新作業を行い、万が一のトラブルを未然に防ぐことが大切です。
マイナポイント・健康保険証機能への影響と再設定ガイド

マイナポイントへの影響
マイナンバーカードを紛失すると、マイナポイントの申込みや利用が一時的にできなくなる可能性があります。
特に、既に付与されているポイントは失効しませんが、新規申請や別サービスへの登録変更は、カード再発行が完了するまで待つ必要があります。
さらに、カードの利用者証明用電子証明書も新しいものに置き換えられるため、以前に登録していた端末やアプリで再ログインや再登録が必要になるケースがあります。
再発行されたカードを使って再度マイナポイントの申込みや利用者情報の更新を行い、その際に暗証番号や関連するアカウント情報を準備しておくと手続きがスムーズです。
健康保険証機能への影響
マイナンバーカードに健康保険証としての機能を登録していた場合、紛失時にはその機能も一時的に利用できなくなります。
これは、カードに紐づいた電子証明書や認証情報が失効するためで、再発行されたカードに改めて設定し直す必要があるためです。
医療機関での受診時には、再発行が完了して新しいカードを設定するまで、従来のプラスチック製健康保険証を提示して受診する必要があります。
特にオンライン資格確認対応の医療機関では、カードをかざして認証する方式が使えなくなるため、事前に保険証を持参する準備をしておくと安心です。
再設定の仕方
カードが再発行されたら、マイナポータルや対応窓口でマイナポイントや健康保険証機能の再設定を行います。
再設定には暗証番号や本人確認書類が必要になるため、事前に準備しておくとスムーズです。
特に、マイナポイントの場合は対象の決済サービスや利用アプリ内での再登録手順も踏む必要があるため、事前にログイン情報やパスワードを確認しておきましょう。
健康保険証機能の再設定では、医療機関や薬局でスムーズに利用できるよう、設定完了後に動作確認をしておくことをおすすめします。
また、各サービスによって再設定の手順や必要書類が異なる場合があるため、必ず公式サイトや案内資料で最新の方法と注意点を確認してから行動することが大切です。
子ども・高齢者がマイナカードを紛失したときの対処方法

子どもが紛失した場合
子どもがマイナンバーカードをなくした場合は、保護者が代理で停止手続きや届出を行う必要があります。
特に未成年の場合は、自分で連絡や申請をするのが難しいため、保護者が迅速に対応することが重要です。
まずは、マイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してカードの機能を停止し、カードが不正に使われないようにします。
その後、警察に遺失届を提出して受理番号を取得しましょう。
再発行の際には、保護者と子どもの本人確認書類、警察の受理番号、場合によっては戸籍謄本など親子関係を証明する書類が必要になることがあります。
また、自治体によっては窓口での手続き時に子どもの同席を求められたり、署名や押印が必要になるケースもあります。
事前に自治体の公式サイトや電話で必要書類や流れを確認しておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。
高齢者が紛失した場合
高齢者がマイナンバーカードをなくした場合、本人による停止や再発行などの手続きが難しいこともあります。
そのような場合は、家族や成年後見人、介護者などの代理人が速やかに対応することが重要です。
代理申請には委任状や代理人の本人確認書類、本人との関係を示す書類(戸籍謄本や住民票など)が必要で、自治体によっては追加の証明書類を求められることもあります。
高齢者施設に入居している場合は、施設職員が手続きに同行したり、必要書類の準備をサポートしてくれる場合があります。
また、本人が外出しない生活を送っている場合は、カードを日常的に持ち歩かず、鍵のかかる引き出しや金庫など安全性の高い場所に保管することが望ましいです。
再発行後は暗証番号の管理も含め、再紛失防止策を徹底することで安心して利用できます。
共通の注意点
子どもや高齢者の場合、カードの管理が本人任せになっていると紛失の危険性が高まります。
そのため、家族や周囲の人が定期的にカードの所在を確認し、使用頻度が少ない場合は鍵付きの引き出しや耐火金庫など安全な場所で保管する習慣をつけることが重要です。
また、持ち出す際には使用目的を家族に共有し、外出から戻ったら速やかに元の場所に戻すルールを設けましょう。
さらに、万が一に備えて停止手続きや再発行の流れ、必要な連絡先や書類リストを紙やスマホにメモして家族間で共有しておくと、実際に紛失したときも慌てず落ち着いて対応できます。
紛失を防ぐための予防策

持ち歩く頻度を減らす
必要なときだけ持ち出し、普段は安全な場所に保管します。
特にマイナンバーカードは日常的に使う機会が限られているため、常に財布やカバンに入れておく必要はありません。
役所での手続きや本人確認が必要な場面など、具体的な使用予定があるときにだけ持ち出す習慣をつけましょう。
また、持ち歩くときは目的地までの移動中に落とさないよう、カードの収納場所を決めておくことが大切です。
帰宅後はすぐに決まった保管場所に戻すルールを作ることで、置き忘れや紛失のリスクを大幅に減らせます。
ICカードケースやストラップを活用
財布やカードケースにしっかりと固定しておくことで、外出先での落下や置き忘れによる紛失のリスクを大幅に減らせます。
例えば、伸縮性のあるリール付きストラップや、ケースごとバッグの内ポケットに留められるチェーンタイプのものを選ぶと、取り出しやすく、かつ不意の落下も防げます。
また、透明タイプのICカードケースなら、中身を出さずに確認や読み取りができるため便利です。
日常的に持ち歩く方は、デザイン性と機能性の両方を備えたアイテムを選ぶことで、使いやすさと安心感を両立できます。
保管場所を固定
自宅での置き場所を決め、家族にも共有しておきましょう。
例えば、鍵付きの引き出しや耐火金庫など、安全性の高い場所を選ぶと安心です。
家族にも場所を伝えておくことで、緊急時に誰でも取り出せるようにしておくと便利です。
さらに、保管場所を変更する場合は、家族全員に必ず知らせるようにし、保管場所を記録しておくと、置き忘れや紛失のリスクをさらに減らすことができます。
よくある質問(FAQ)

Q1:紛失後に見つかったら再発行をキャンセルできる?
→ 手続きの進行状況によります。
申請からカード作成工程に入ってしまうとキャンセルできないことが多く、手数料も返金されない場合があります。
そのため、紛失後に発見した場合は、できるだけ早く自治体窓口や担当部署に連絡し、状況を説明しましょう。
カードがまだ印刷や発行準備の段階に入っていなければ、再発行を止められる可能性もあります。
Q2:再発行中に手続きが必要になったら?
→ マイナンバー通知カードや住民票の写しで代用できる場合があります。
たとえば、役所での各種申請や銀行口座の開設、保険手続きなど、マイナンバーカードが必要とされる場面でも、これらの書類で本人確認や番号確認が可能なケースがあります。
手続きによっては、通知カードと本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)をセットで提示する必要があることも多いので、事前に必要書類を確認して揃えておきましょう。
また、住民票の写しは自治体窓口だけでなく、コンビニ交付サービスで取得できる場合もあるため、急ぎのときには活用すると便利です。
Q3:紛失を届け出なかった場合の危険性は?
→ 不正利用の恐れがあり、重大なトラブルに発展する可能性があります。
届け出をしないまま放置すると、誰かに拾われた場合に身分証として悪用されたり、オンラインでの本人確認に使われて不正な契約や取引が行われる危険性があります。
こうした被害は後から発覚することも多く、その際には警察や金融機関、関係機関への連絡・調査など、解決に多くの時間と労力が必要になります。
さらに、届出をしていなかったことで被害の補償や対応が難しくなるケースもあるため、紛失に気づいたら必ず速やかに届出を行うことが大切です。
Q4:マイナンバーの番号は変更できる?
→ 原則として変更はできません。
マイナンバーは一人に一つ付与されるもので、生涯同じ番号を使うことが基本となっています。
ただし、番号の漏えいや悪用が実際に確認された場合、またはその恐れが極めて高いと判断されるやむを得ない理由があるときには、変更申請が認められることもあります。
変更を希望する場合は、まず自治体窓口に相談し、必要書類や具体的な手続き方法、審査にかかる期間などを確認しましょう。
申請には状況を証明する資料や警察への届出記録などが求められる場合が多く、審査が厳格に行われるため、事前の準備と説明が重要になります。
Q5:紛失届を出す前に見つかったらどうする?
→ すぐに利用を再開できるわけではなく、安全のために自治体窓口でカードの状態を確認してもらいましょう。
紛失の届出を出す前でも、一度カードの機能を停止している可能性や、内部の電子証明書に問題が発生している場合があります。
そのため、職員による動作確認や安全性のチェックを受けることが重要です。
場合によっては機能の再設定や電子証明書の再発行、暗証番号の再登録などが必要になることがあります。
こうした対応を経て初めて、安心してカードを再び利用できる状態になります。
Q6:海外でマイナンバーカードを紛失した場合は?
→ 現地の日本大使館や総領事館にまず連絡し、紛失の事実を伝えてください。
必要に応じて現地で警察への届出を求められることもあります。
帰国後には、居住地の自治体で正式な再発行手続きを行いますが、その際に海外での紛失を証明する書類が必要になる場合があります。
また、海外からでもマイナンバー総合フリーダイヤルやオンライン経由で停止手続きが可能なため、総務省の公式サイトで詳しい手順を確認し、できるだけ早くカードの機能を停止しましょう。
こうすることで、海外滞在中の不正利用の危険性を最小限に抑えることができます。
まとめ|正しい手順で安心・安全に対応

1.停止手続き(電話またはオンライン):まずは悪用を防ぐためにカードの機能を止めることが最優先です。
2.警察への遺失届:正式な記録を残し、受理番号を取得しておくことで後の手続きがスムーズになります。
3.市区町村で再発行申請:必要書類をそろえ、期限や費用、受け取り方法を確認してから申請します。
4.再発行後の情報更新と予防策:カード情報を利用している各種サービスへの届け出を行い、同時に紛失防止の習慣を取り入れます。
これらの手順をしっかりと理解し、順序立てて行動することで、万が一の紛失でも慌てずに対応できます。
記事をブックマークしておけば、いざという時にすぐ見返せて安心です。
家族や知人とも共有しておくと、周囲の人が同じ状況に陥った際にも役立ちます。
参考リンク(公式情報)
マイナンバーカード全般に関する制度や申請方法、よくある質問などを網羅的に掲載している公式ページです。紛失時の手続きや再発行に関する情報もこちらから確認できます。
オンラインでの停止手続きや各種申請ができる便利なポータルサイトです。利用方法や必要な準備、ログイン方法なども詳しく案内されています。
全国の都道府県警察における落とし物や忘れ物の届出方法、検索方法をまとめた公式案内ページです。
紛失物をできるだけ早く見つけ出すための手順や、届け出先の一覧、オンライン検索のリンクなどが掲載されています。
警察に遺失届を出す際の必要事項や注意点も確認できるため、カードをなくしたときは必ずチェックして活用しましょう。
※本記事は2025年8月15日時点の公式情報をもとに作成しています。手続きの方法や必要書類、費用の金額、申請可能な窓口や受付時間などは自治体ごとに異なる場合があります。また、制度や手続きの流れが将来的に変更される可能性もあるため、この記事を参考に行動する際には、必ず最新の公式情報や自治体からの案内をご確認ください。